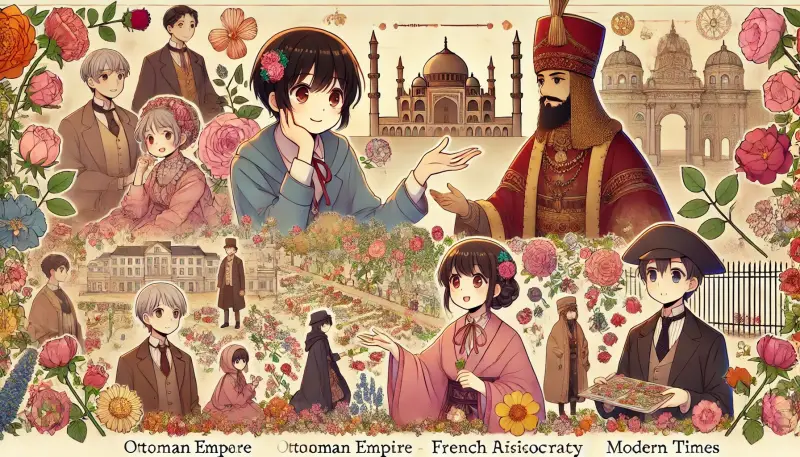「花言葉 誰が決めた」と検索している人は花言葉がどうやって決まったのか、その歴史や由来が気になっていることでしょう。また、花言葉とはそもそもなぜ作られたのか、その歴史や起源にも興味が湧いてくると思います。
実は、花言葉のルーツは海外にあり、起源は日本ではなくオスマン帝国に遡ります。本や一覧サイトなどで調べるとギリシャ神話に由来した面白い花言葉や、ちょっと怖い意味を持つ花言葉まで様々です。
この記事では、そんな花言葉が誰によってどのように決められ広まってきたのかを詳しくご紹介します。
- 花言葉には明確な決定者が存在しない理由
- 花言葉の起源と広まった経緯
- 花言葉が地域や文化で異なる理由
- 花言葉を決める主な由来や方法
花言葉は誰が決めた?歴史や起源を徹底解説

- 花言葉の起源はどこ?
- 花言葉はなぜ作られたのか
- 日本での花言葉の歴史
- 花言葉はどうやって決めた?
- 花言葉を一覧で知るには?
花言葉の起源はどこ?

花言葉の起源は、17世紀ごろのオスマン帝国(現在のトルコ周辺)にあると言われています。
なぜならば、当時のオスマン帝国には「セラム」と呼ばれる独特な習慣があり、これが後の花言葉の元になったからです。
具体的には「セラム」という習慣では、小箱に花や小物を入れて相手に贈り自分の想いを伝えていました。当時は、恋愛の気持ちを言葉で伝えることが難しかったため、人々は品物に意味を込めてコミュニケーションを取っていたのです。この文化がヨーロッパへ伝わり、特にフランスで人気となった結果、現代に繋がる「花言葉」が発展していきました。
ただ、花言葉が世界中に広がる過程で、地域や文化によって解釈や意味が変化したことには注意が必要です。
花言葉はなぜ作られたのか

花言葉が作られた最大の理由は、「言葉で伝えにくい想いや感情を花に託すため」です。
もともと人は、気持ちや感情を直接的に表現することに抵抗がありました。そのため、花を通じて相手に想いを伝える方法が広まりました。
例えば、愛情や感謝の気持ち、時には嫉妬や別れの悲しみのような負の感情であっても、花言葉を使えば間接的に伝えることができます。一方で、花言葉には「公式な決定機関」が存在しないため、地域や時代によって意味が異なることがあります。この点を考慮すると、花言葉を活用する際は相手の文化や価値観も理解した上で選ぶのが良いでしょう。
日本での花言葉の歴史

日本における花言葉の歴史は、明治時代以降に西洋文化とともに伝わったことが始まりです。
実際、それ以前の日本にも「花に対する感性」はありましたが、現在のような体系化された花言葉はありませんでした。
西洋の花言葉が伝わった後、日本独自の感性が加わり、新たな意味を持つ花言葉が次々と生まれました。例えば、桜は日本特有の美意識を反映し、「精神美」や「優美な女性」という花言葉になっています。
ただし、注意点として、同じ花であっても日本と西洋では意味が異なる場合があります。菊の花が日本では高貴さを象徴する一方、西洋では死や喪を連想させるように、花言葉を使う場合には相手の文化背景を意識する必要があります。
花言葉はどうやって決めた?
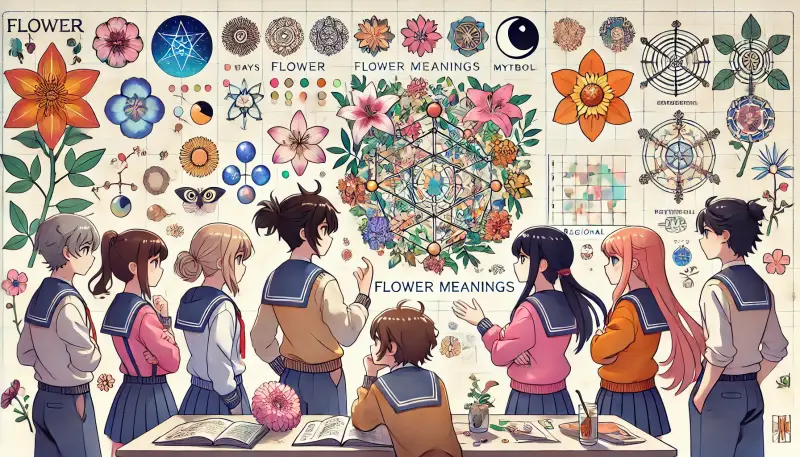
花言葉の決定には明確な公式ルールや決定機関はありません。実際は、長い年月をかけて自然に広まり人々の間で共有されていったものです。
主に花言葉の決め方には、以下の4つの由来があります。
一つ目は「神話や伝説に由来するもの」です。例えば、水仙(ナルシス)はギリシャ神話に出てくるナルシスという美少年にちなんで「うぬぼれ」という意味になりました。
二つ目は「花の姿や特性に由来するもの」です。パンジーは下向きに咲く姿が考えごとをしているように見えるため、「物思い」という花言葉が付きました。
三つ目は「色が持つ一般的なイメージを基にしたもの」です。例えば赤いバラは情熱や愛情を、黄色いバラは嫉妬を意味するなど、花の色のイメージがそのまま花言葉になっています。
そして四つ目は「文化や地域の価値観による違い」です。日本ではチューリップが「思いやり」を表しますが、西洋では「理想の恋人」と意味が異なります。
このように、花言葉の決め方には複数の要素が絡み合っているため、使用する際には花の背景まで意識しておくことが大切です。
花言葉を一覧で知るには?

花言葉を一覧で知りたい場合、まずはインターネットの花言葉サイトや辞典を利用するのが簡単で便利です。現在では、無料で多数の花言葉一覧サイトが公開されており、花の名前や色から簡単に検索できます。
例えば、『美しい花言葉・花図鑑』などの書籍では、基本的な花から人気の花まで広く網羅されているため、手元に置いておくと便利です。また、園芸専門店や花屋さんがウェブ上で提供している花言葉一覧も信頼性が高く、最新情報を得やすいでしょう。
ただし、注意すべき点として、花言葉は国や文化によって異なることがあるため、複数の情報源を比較して確認するのが良い方法です。単純に花言葉を覚えるだけではなく、花言葉が生まれた背景や由来も合わせて学ぶことで、より深い理解につながります。
花言葉は誰が決めた?面白い由来や怖い話も
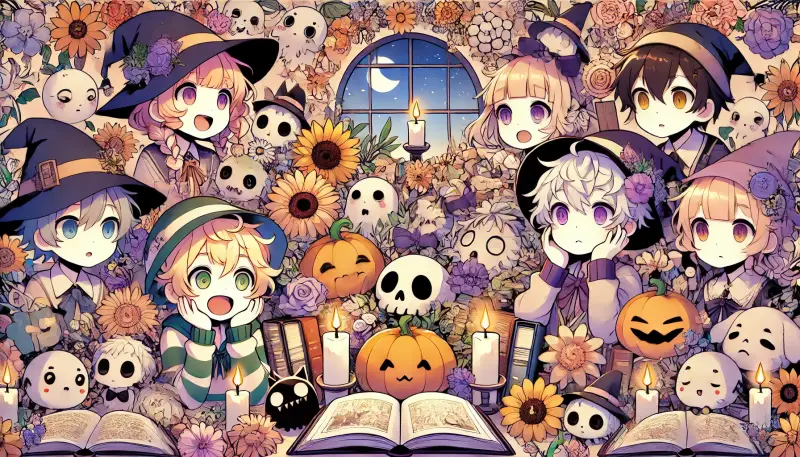
- ギリシャ神話の面白い花言葉
- 実は怖い花言葉の話
- 色によって違う花言葉一覧
- 花業界が決めた花言葉も?
- 花言葉の決め方が載った本
- SNSで変化する花言葉
- 花言葉の未来はどうなる?
ギリシャ神話の面白い花言葉

ギリシャ神話から生まれた花言葉には、面白くロマンティックな由来を持つものがあります。
ギリシャ神話では、多くの神々や英雄が登場し、そのストーリーと結びついて花言葉が誕生しました。
例えば、アネモネという花には「はかない恋」という花言葉があります。この花言葉は、美と愛の女神アフロディテが、美青年アドニスを失った際に流した涙から咲いた花がアネモネだと伝えられているからです。美しい花が悲しい物語と結びついているという点で興味深く感じられるでしょう。
また、水仙(ナルシス)の花言葉「うぬぼれ」もギリシャ神話に由来します。美青年ナルシスが水面に映る自分の姿に見とれてしまい、そのまま命を落としてしまったという伝説がもとになっています。
花言葉の意味を知ると同時に、背景にある神話を学ぶことで、より興味深く花を楽しめるでしょう。
実は怖い花言葉の話
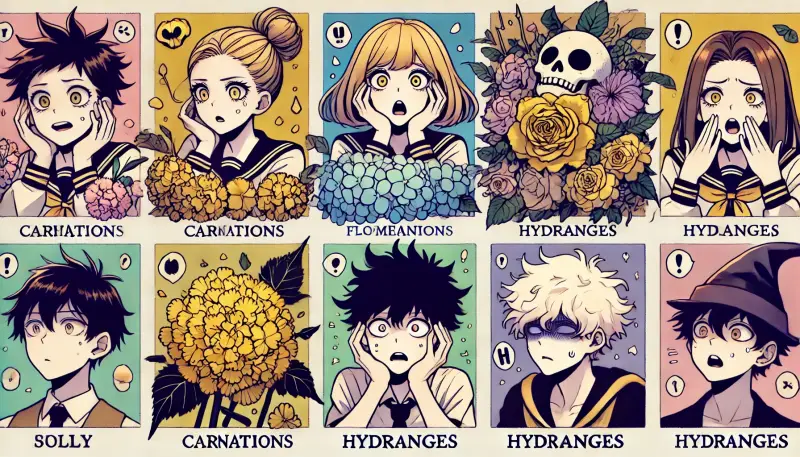
花言葉には、華やかなイメージとは裏腹に、怖い意味や由来を持つものもあります。
花を贈る際に、見た目だけで選んでしまうと意図せずネガティブなメッセージを伝えてしまう危険性があるため注意が必要です。
例えば、黄色いカーネーションには「軽蔑」や「嫉妬」という花言葉があります。これは西洋文化圏で黄色が裏切りや嫉妬を象徴する色とされているためです。また、アジサイには「移り気」「浮気」という花言葉があります。アジサイの色が時間とともに変化してしまう様子が、人の気持ちの変化に例えられたのが由来です。
もちろん、これらの花を使ってはいけないわけではありませんが、贈る相手やシチュエーションには慎重に配慮しましょう。花をプレゼントする際には、その花に込められた意味を事前に確認しておくことが重要です。
色によって違う花言葉一覧

花言葉は、同じ種類の花でも色が異なると意味が大きく変わります。
これは花の色が持つ一般的なイメージに基づいて、花言葉が決められることが多いためです。
例えば、バラの場合、赤は「情熱的な愛」、ピンクは「上品・感謝」、白は「純潔・尊敬」、黄色は「嫉妬」といったように、色によって全く異なる印象になります。また、カーネーションも同様に、赤色は「母の愛」、ピンクは「感謝」、黄色は「軽蔑」を表現します。
注意したいのは、同じ花でも色を間違えてしまうと、相手に誤解される可能性がある点です。贈り物として花を選ぶときには、花の種類だけでなく、色ごとの花言葉をしっかり確認して選ぶとよいでしょう。
花業界が決めた花言葉も?
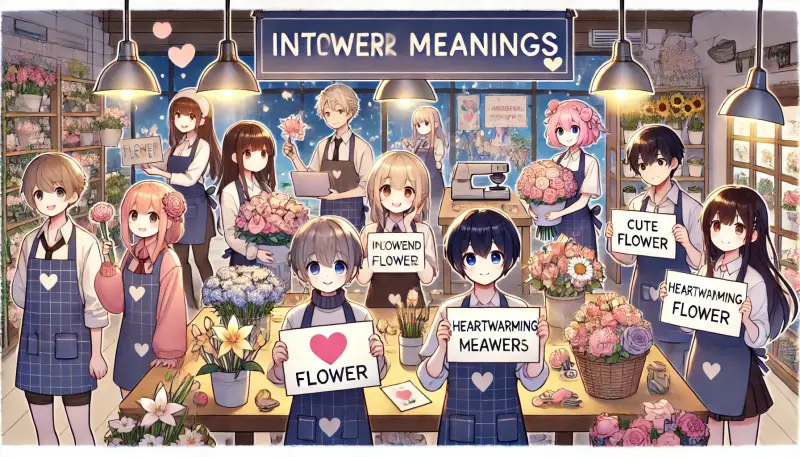
実際には、花業界のマーケティング戦略によって生まれた花言葉も多く存在します。花業界が販売促進の目的で、特定の花に魅力的な花言葉を設定し広めた例があるからです。
有名な例としては、母の日の「赤いカーネーション」が挙げられます。「母の愛」という花言葉をつけることで、母の日の定番となり、現在まで広く親しまれています。また、新しく品種改良された花に対しても、開発者や販売会社がオリジナルの花言葉をつけて市場に出すことが多くあります。
ただし、こうしたマーケティング由来の花言葉は、場合によっては本来の由来や一般的なイメージと異なることもあります。そのため、花言葉を選ぶときには、宣伝文句に踊らされず、本来の意味や背景を調べてから使うとよいでしょう。
花言葉の決め方が載った本
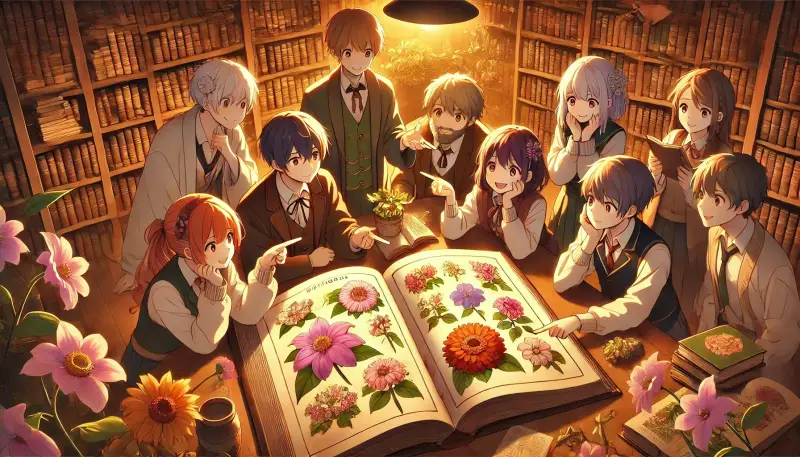
花言葉がどのように決められたか詳しく知りたい方には、花言葉辞典や専門書がおすすめです。
具体的には、古くから知られている『Le Langage des Fleurs』(マダム・シャルロット・ド・ラトゥール著)がよく挙げられます。この本は1819年にフランスで出版された最初の花言葉辞典であり、花言葉がどのように体系化され、ヨーロッパで広まったかを知ることができます。
また、日本語で手軽に読みたい場合は『美しい花言葉・花図鑑』などの書籍が便利です。ただ、こうした本は情報量が非常に多いため、初心者が読む際には一気に全部を覚えようとせず、気になる花や好きな花から徐々に調べるのがおすすめです。
SNSで変化する花言葉

最近では、SNSの普及によって花言葉の意味が新たに加わったり変化したりすることも増えてきました。これは、インフルエンサーや一般ユーザーが独自の花言葉を発信し、多くの人々がそれを共有するためです。
例えば、「青いバラ」は本来「不可能」という花言葉を持っていますが、最近ではSNSを通じて「奇跡」や「神秘的な愛」という新たな意味が広まりました。また、特定のイベントやキャンペーンに合わせて新たな花言葉が設定され、一時的に広まることもあります。
しかし、SNSで広まった花言葉は情報の出所が不明確な場合が多いため注意が必要です。SNS発の花言葉を利用する場合は、元々の花言葉との違いや相手が持つ印象を慎重に考えましょう。
花言葉の未来はどうなる?

花言葉は今後、現代の価値観や社会の変化に応じてさらに多様化していくと予想されます。特に最近では、環境問題や多様性を意識した花言葉も登場しています。
例えば、環境に配慮した方法で栽培された花には「エコフレンドリー」や「持続可能性」を象徴する意味が付けられています。さらに、今後はバーチャル空間で花を贈り合うようなデジタル時代の花言葉も生まれる可能性が高いでしょう。
ただし、このように新しい意味が増えることで既存の花言葉と混乱する場合もあるため、贈る側も受け取る側も柔軟に考える姿勢が大切になります。新旧の花言葉を上手に使い分けながら楽しむとよいでしょう。